- ホーム
- エグゼクティブセミナー
- 受講者の声
受講者の声
受講者の声

第133回経営幹部セミナー
北川 晶 氏(第133回経営幹部セミナー受講)
第一三共ヘルスケア株式会社
ブランド推進本部 H&B 推進部 開発グループ長
経営幹部セミナーを受講した目的
私はこれまでコンシューマー向けヘルスケア製品の開発を中心に経験を積んできましたが、社会や市場の変化が加速する中で、事業における課題や自らの役割も変化し、これまでの経験や知識だけでは対応が難しいと感じる場面が増えてきました。会社の推薦により本セミナーを受講することとなり、経営に必要な知識を体系的に学ぶことで、自分に不足している力を整理し、ぶれない軸を持ちつつ柔軟に判断できる高い視座と対応力を身につけたいと考えました。また、異なる業界や企業の方々との交流を通じて多様な視点や価値観に触れ、新たな発想を得ることも大きな目的でした。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
まず、経営に必要な知識として自分に不足しているものを整理することができました。「ケース」学習では、事前学習で経営者の意思決定プロセスを追い、背景にある環境変化や戦略を自分なりに解釈してグループディスカッションに臨みましたが、討議の中で自分では思い至らなかった視点や考え方に触れるたびに新たな気づきを得ることができました。また、講義では多様な意見を交わしながらテーマの本質を探る過程が非常に刺激的でした。これらを通じて、経営者やマネジメント層の理念や価値観が組織運営やビジネスに与える影響を理解し、知識だけでなく感覚的にも経営とは何かをイメージできたように思います。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
限られた時間の中で多くのケースに取り組み、先生方や仲間から多くの刺激を受けたことは大変貴重な経験であり、私に大きな変化をもたらしました。「ぶれない軸を持ちつつ柔軟に判断できる高い視座と対応力」を身につけるために、今後意識すべきことや学ぶべき方向性が明確になったと感じています。これからも学びを重ね、視野を広げながら、変化の激しい社会の中で自社が提供すべき価値とは何かを考えていきたいと思います。そして、組織全体を巻き込みながらそれを実現し持続的な成長につなげていくことを目指します。

第132回経営幹部セミナー
山下 美保 氏(第132回経営幹部セミナー受講)
マナック株式会社
代表取締役社長執行役員
経営幹部セミナーを受講した目的
上海法人で総経理を務めた後、日本本社の社長に就任しましたが、本社全体を俯瞰する力や経営の基礎を体系的に学ぶ必要性を強く感じていました。
当社には本セミナーを受講者した社員が複数いますが、経営に関する専門知識の習得に加え、実践的な問題解決力や意思決定力の向上、多様なバックグラウンドを持つ参加者とのネットワークの構築が可能との話を聞き、この経験は経営判断や組織運営に大いに役立つと考え、受講させて頂きました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
戦略・財務・組織・リーダーシップなど、幅広い経営の視点を体系的に学びました。
グループディスカッションを通じて、業種や部門を超えた視点で戦略を考える力が養われ、企業を多角的に捉える思考が身につきました。
また、「良い企業とは?」「良い経営者とは?」といった根本的な問いに向き合う貴重な機会にもなりました。
このセミナーを通じて、自身のリーダー像や経営の軸を見つめ直し、経営者としての判断力や視座を深めることができました。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
変化の激しい環境にも柔軟に対応し、意思決定の質を高めることで、迅速かつ的確な対応を実現していきます。
また、リスクを抑えつつ企業が持続的に成長していくためには、チャレンジを恐れず挑み続ける姿勢が不可欠だと考えています。
組織全体の連携や情報共有を促進し、経営の透明性と効率性を高めることで、強固な企業基盤の構築にも貢献します。
こうした取り組みを通じて、企業価値の向上と市場での競争力強化を目指していきます。
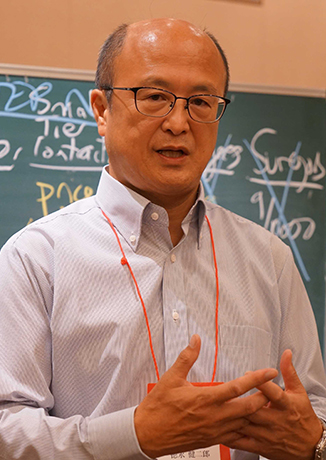
第70回高等経営学講座
徳永健二郎 氏(第70回高等経営学講座受講)
株式会社中電工
執行役員、鳥取統括支社長
高等経営学講座を受講した目的
設備業界は、現代社会の基盤を支える重要な分野だと考えています。その業界では、時間外労働の上限規制など社会情勢の変化や、人手不足対策としてのDXの推進など技術革新により、大きな変革期を迎えるなかで、「企業としてどうあるべきか」を考えていたとき、「様々な業界から、同様な立場の受講者が集まり、様々なケースについてディスカッションする講座がある」ことを聞き、他業種のリーダーの方たちが持たれている考えや、その判断要素等を聞きたいと思い、受講を決めました。
高等経営学講座で得たもの、学んだもの
外部との接触が遮断された環境下で、総合経営・財務・マーケティング・意思決定等のケースを基に、個人研究・グループディスカッション・クラスディスカッションという3つのステップを踏むことで、自分自身の統合力・洞察力・戦略力を大きく鍛えられました。個人研究の段階では、何度も読み込むことで理解が進み、事象を整理する中から、自分の意見を構築することができました。その後のディスカッションでは、他の受講生の考え・意見を聞くことで、自分の思考の浅さを痛感するとともに、講師の巧みな誘導により、より明確に、より現実的に、より創造的に物事を考えるようになりました。
今後、学んだものを業務でどのように活かしていくのか
与えられたケースとその設問は、経営に関する幅広い分野に亘るものであり、それぞれを作成された専門の教授や、業種の異なる方たちとディスカッションする中で、自分のもつ固定概念が壊され、物事の捉え方・考え方、他者の意見を活かす重要性を学びました。
今後、直面するであろう意思決定の場では、一方的に方向を定めるのではなく、目的・範囲・競争優位性等を論議するなかで方向を定めるなど、私の得た体験が、組織内に浸透するよう運営していきたいと思います。

第131回経営幹部セミナー
佐藤 亜由子 氏(第131回経営幹部セミナー受講)
ナミックス株式会社
経営企画室 シニアチームリーダー
経営幹部セミナーを受講した目的
私は入社以来、技術開発の立場からお客様が抱える課題を自身が提供する製品特性で解決すべく検討してきました。3年前に経営企画という全社横断での方針、戦略を検討する部門に異動となり、これまでとは異なる知識、視点での課題解決力が必要であると痛感していました。グローバル市場における事業経営を継続する為には著しく変化する外部環境への対応力が求められ、長期的な視点で企業が進むべき方向性を考え、戦略を立案していかなければなりません。この研修を通じて経営の基礎を学び、自身の視座や思考の変革、向上を行いたいと考え、研修に参加させていただきました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
設定されたケースは財務、マーケティング、組織マネジメント等、テーマ分類されたものでしたが、それらは互いに関連しており、最終的にはひとつが欠けると回らなくなるという経営全般の仕組みを学べるものでした。私が課題としている質の高い迅速な意思決定に必要な考え方についての内容もあり、それらは日々の業務における判断が困難な状況での助けとなり、全体最適のために目下の課題にどう取り組むべきなのか、意識していきたい内容でした。ケース講義において、発散する意見や発言を参加者全員が理解し、納得できる共通言語に置き換え、収束される講師の先生方のファシリテートは大変興味深く、様々な階層との議論において重要であり、今後習得していきたいスキルのひとつです。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
クラス討議は日常ではありえないような困難な課題に対し、無意味な反論や意見を揃えることではなく、最善のアウトプットを導くことを共通の目的とした時間でした。緊張感の中にもメンバー同士が尊重し合う雰囲気が自然に伝わるような時間、環境が、難しい課題の解決策を導けたと実感しており、この環境創りを社内に共有していきたいと思います。また、業績に直接的には影響しない社会的責任を追求するいくつかの項目において、ケースやクラス討議を通し、自社にとっての取り組む目的、意義を再考することができました。企業価値とは何かを改めて考え、その向上に向けた施策についてこれらの視点を以て検討していきたいと考えております。

第130回経営幹部セミナー
諫山 洋平 氏(第130回経営幹部セミナー受講)
出光興産株式会社
徳山事業所 品質管理課 課長
経営幹部セミナーを受講した目的
現在、自部署のマネジメントともに、約500名が所属する事業所の組織変革に取り組んでいます。これまでの取組みを通じて痛感していることは、事業環境や働き方の価値観が大きく変わる今、従来の知恵の延長線上にない学びと実践が必要ということです。しかし、実務での学びや、書籍の独学、単発の研修ではどうしても学習効果に限りがあるとも感じていました。本セミナーでは、経営に関する広く深い最新の学術的知見を、ビジネスの現場での実例に関連付けながら議論し学んでいけるということで、大きな期待を抱き受講致しました。また、様々な業界・職種の方々との交流を通じて、これまで気付いていない自分の強みや弱みを見出す機会とすべくセミナーに臨みました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
期待を上回る、充実の内容でした。組織マネジメント、財務会計、マーケティング、経営環境等のテーマのケーススタディにより、予習で考え抜いたはずの自らの結論の不足点や、今後備えるべき大局的観点が多くあることを痛感しました。クラスディスカッションでは、体系的な内容を踏まえつつ、参加者の関心と先生方の研究内容が掛け合わさり偶発的に脱線し、思いもよらぬ学びがあったのも大きな収穫です。
先生方は、休憩時間も質問や意見交換に熱心に応じて下さり、対話の中で、別の講義の内容とつながることも多々ありました。例えば、役割分担の観点で学んだアカウンタビリティの概念が、別の講義では、心理的安全性と組織の業績を両立させる重要因子だと学びました。本セミナーは、このような横断的な学びを得られる点が特に素晴らしいと感じました。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
ビジネスでの日々の判断に活かせる重要な学びの連続でした。組織マネジメントや生産政策の内容はすぐ職場で実践していきますし、全ての内容を、これまで関与できていなかった領域や階層の判断に参画して活用していきたいと思います。そして、体系的な理論と多面的視点をもとに、より柔軟かつ大局的に判断できるよう、自分自身をさらに磨いていきます。
なによりも今回、学ぶことの楽しさ、ビジネスの奥深さや面白さを改めて強く感じることが出来ました。この学びと楽しみを周囲のマネジャーやメンバーに広め、学びの輪を組織に広めていきます。そして、新たな価値を生む組織となり、事業を通じて社会的利益を大きくしていくことに貢献したいと思います。
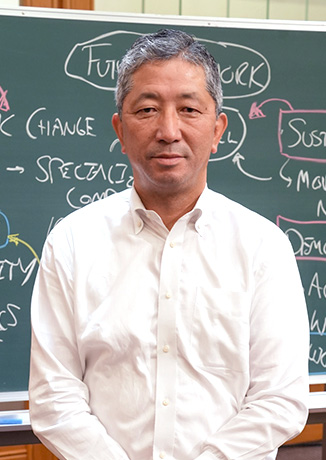
第69回高等経営学講座
竹中 秀文 氏(第69回高等経営学講座受講)
株式会社大林組
京都支店 執行役員 京都支店長
高等経営学講座を受講した目的
現在の建設業は価格高騰、担い手不足、労働時間短縮などの働き方改善など自ら抱える課題が多く、コロナ禍、円安等今後不透明な状況も相まって、不確定要素の渦の中にいます。
そのような環境の中で常に自社としての姿勢を明確にし、顧客の要望に応えアドバイスを行うために、刻々と変化する状況分析やその中での瞬発的な意思決定が求められております。
本セミナーは、合宿形式で集中的にケースメソッドで、厳しい経営の修羅場を疑似体験することができ、今後の業務に大いに応用できると考えました。
高等経営学講座で得たもの、学んだもの
個人研究、グループディスカッション、クラスディスカッションそれぞれにおいて非常にハードで得るものが大きいと感じました。
個人研究は私にとって最重要であり、自分の意思を固める場でした。前日に集中力をもって資料を読みこむだけでなく、自分の考えを絞り出すために脳をフル活動させました。
グループディスカッションは活発な議論で自分の意思を修正する場でした。異業種の自分より経験豊富な方々のご意見に刺激を与えられたのは収穫でした。
クラスディスカッションは異業種の方々のお考えやファシリテータである講師陣のご指導をもとに、もし自分が経営者であった場合にどう行動し判断していくべきだったか最終的な自分の意思を固める場でした。
このように毎日が自分にとってトライアンドエラーの連続であり、限られた時間を毎日フル活用する充実した7泊8日でした。
また初めて出会う方々とのディスカッションを通じたファシリテートや知識や経験が少ない状況の中でどのように議論に切り込んでいくかといったメンタルトレーニングを行うことができ、自分の弱点の強化につながったと確信しています。
今後、学んだものを業務でどのように活かしていくのか
今回のケースメソッドですべてにおいて共通して重要と言えることは、自然体で物事を考えること、公平、平等に判断すること、倫理観をもつことです。
これは業種や職種が異なっても共通なことで、私のなりわいとする建設業についても日頃から重視していることです。経営の根本はここにありとっても過言ではないと思います。
今後はさらに異業種についてアンテナを張り、自分に置き換えた時の判断ができるかを課題として取り組みたいと考えています。
建設業のステークホルダーは多業種にわたり、あらゆる業種のケースメソッドを通じて顧客の問題点に入り込むとともに、建設業として解決する領域を広げることにも効果があると考えております。

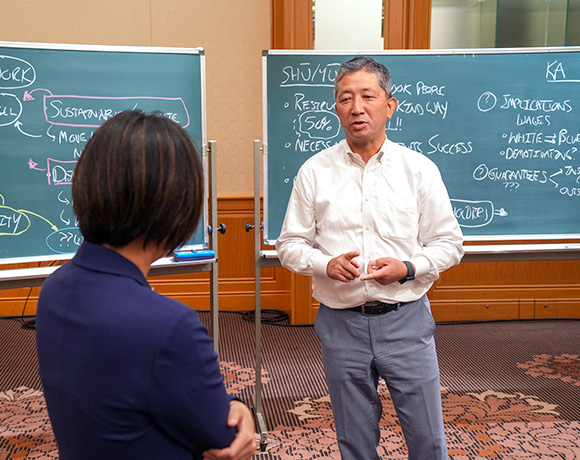
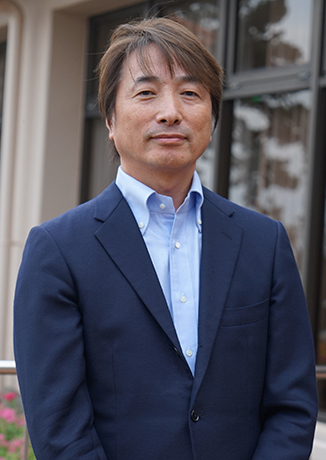
第129回経営幹部セミナー
徳島 茂 氏(第129回経営幹部セミナー受講)
スープリームスインコーポレーテッド株式会社
営業部 取締役COO
受講した目的
ファッションを中心に扱う専門商社・八木通商(株)に入社し、アジア(中国・香港)での衣料品の物作りから始まり、
イタリア・ミラノでの勤務を経て、営業責任者として欧米のファッションブランドを日本市場で販売する業務を担ってまいりました。
欧州企業とのジョイントベンチャーでの勤務等を経て現在は関連会社のスープリームスインコーポレーテッド社に所属し、
欧州のブランドを日本国内で販売する業務に従事しております。
今までの業務を通じて、営業面で活用するKPI等マーケティングや経営に関しての知識をある程度得てきたと考えておりますが、
managementを担う立場として更にレベルの高い考え方、知識を得るため今回セミナーに参加させて頂きました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
今回のセミナーに参加させて頂き、そこで得たものとして、ディスカッションを通じて答えを導き出す思考法、
6日間集中して課題に取り組むことによる集中力といった点に加え、違う業界の皆様とのネットワークがあります。
金融、工業、食品、出版、シンクタンク等幅広い業界の方々との交流は自身の知見を広める良い機会となりました。
学んだものとしましては、高いレベルで研究されてきた経営に関する知識や考察方法、
企業経営のポイント、財務を意識した企業経営、経理的資料へのアプローチ方法、多様性・包摂性の考え方等、
非常に参考になる内容ばかりでした。
学んだものを職務でどのように活かしていくか
前述の通り現在当社は欧州のファッションブランドを日本に輸入し販売しております。
当グループのTop managementのフィロソフィーとして、ブランドを資産と考え、その価値を高める必要がある、
という言葉があります。単なるTradingでは無く、Brand holderとの協働を通じて、より高いポジションへと昇華させることを目指すのですが、
今回のセミナーを受講し、今後欧州側と議論をする際の準備や新規案件を提案する際のアプローチ方法に活かせると感じました。
今回のセミナーで学んだ知識や思考方法を礎として、更に自己研鑽に励み組織の利益に貢献したいと考えております。

第128回経営幹部セミナー
野口 雅司 氏(第128回経営幹部セミナー受講)
グローブライド株式会社
フィッシング営業本部 マーケティング一部 副部長
経営幹部セミナーを受講した目的
私は長らく製造・販売業のマーケティング部門で「市場調査」「商品企画」「マーケティング戦略の策定・遂行」「事業戦略の策定・見直し」「組織基盤の整備・向上」などに従事してきました。今春から東京・大阪に分かれるセクションを預かり、更に広範な業務に取り組む中で総合経営や財務会計の知識が乏しく、自身の経験やスキルの偏りを感じることが多くなっておりました。 今回、会社から受講の案内を受け、まず自身の成長を促進するため、固定観念を払拭し全てのことを貪欲に吸収することを意識しました。そして多角的な視点からの俯瞰力を磨き、総合的な判断力を向上させることと、自社の将来に向けたビジョンを描く力の向上を目的としました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
本セミナーのケースメソッド方式は、設問に対する自分の考えを導き出した後に、グループディスカッションを経て、クラスディスカッション・講義に臨むもので、このプロセスによりまず限られた時間内での課題への情報分析力と処理能力が試されます。グループディスカッションは、異業種の方々との議論で自分の視点の狭さを痛感しながらも、考えをブラッシュアップし議論を深める力が磨かれました。合宿中は自分の思考判断が適切かを考え抜くことの連続で、自己と徹底的に向き合う貴重な日々でした。また異業種の皆様から刺激をいただき新たなネットワークを築くことができたことはこの上ない大きな財産となりました。
そして忘れがたいのは先生方の素晴らしさです。掴み語りから惹き込まれ、時間があっという間に過ぎます。学ぶことの面白さを再認識したと同時に、我々に熱いエールを送って下さったと受け止められました。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
今回のセミナーを通じて痛感したのは、ビジョンを持つこととやり抜くことの重要性です。上位者がビジョンを持ち、その共感・共有者を増やす。いざ取り掛かったら最後までやり抜くこと・・・この大切さを深く胸に刻みました。
しかし、その為にはまずビジョンを描く力が重要になります。本セミナーにおいて学んだ多角的な視点、総合的な判断力を高める努力を常に怠らずに磨いて行きます。また、やり抜くという意味では、周囲を巻き込む力と、自身の強い意思が何より重要であると考えます。私自身を磨きながら、私より若い次世代・その次の層の人材育成を通じて、自身を、会社を成長させ、ひいては日本を成長させて行くことに微力ながら貢献できるよう、日々精進を重ねて行きたいと考えております。

第68回高等経営学講座
小西 博子 氏(第68回高等経営学講座受講)
中外製薬株式会社
オンコロジーライフサイクルマネジメント部 戦略1グループ
高等経営学講座を受講した理由
中外製薬(株)に入社以来昨年まで研究本部で創薬研究に従事しておりましたが,今年から後期臨床開発品のライフサイクルリーダーを務めています。日本市場における責任者として,担当プロジェクトの価値最大化に向けたライフサイクルチームの活動をリード・推進する役割です。実験データを主な判断根拠とし比較的明瞭な議論が可能な早期創薬研究の領域から,自分でコントロルしきれない不確実な要素を多く含む判断を求められる役割へ,私にとって非常に大きなキャリアチェンジでした。約1週間集中的にケースメソッドで学べる本セミナーで自分の足りないところを確認しつつ,実践に繋げる学びを持ち帰りたいと思って受講しました。
高等経営学講座で得たもの,学んだもの
教科書的な知識の必要性とその使い方を,ケースを通じて学びました。更に,それらよりも強く印象に残ったのは,経営者やマネジメント層の理念・価値観が組織とビジネスに与える影響でした。とくに,製品やサービスそのものだけでなく,もう少し広い範囲でのビジネスと社会の接点の在り様に経営者の価値観が大きく影響を与え得るということを知りました。ケースから得た視点もありますし,グループのメンバーとの議論で様々な意見に触れて得られた視点も多くありました。自分の携わるビジネスを成立させるための視点は当然のこととして重要ですが,それが社会に与え得る影響を高い視点から考えることも大事であると感じました。
今後,学んだものを職務でどのように活かしていくか
まず経営に関する知識をもっと身につけるため,学習を継続したいと思っています。自分の担うプロジェクトを,より成功の可能性が高い方向への動かすロジックを立てられるようになりたいと考えています。また,ロジックだけでなく,伝え方とその根底にある価値観も重要だと感じましたので,改めて自分の所属する組織の理念とトップの発するメッセージ,そして自分の価値観と,自分たちの組織が社会に届けようとしている価値の一貫性についてもっと深く考えたいと思います。また,伝え方についても自分の中により多くの抽斗を持てるように意識していきたいと思っています。これまでの自分の思考は単純すぎたかもしれません。

第127回経営幹部セミナー
茅野 知弘 氏(第127回経営幹部セミナー受講)
住友商事株式会社
デジタルソリューション事業第二部 部長代理
経営幹部セミナーを受講した目的
総合商社の多岐に亘るビジネスの中では、その実務も「事業戦略の策定・見直し」、「市場調査」、「マーケティング戦略の策定」および「会計知識に基づく企業評価」等々、広範囲に及びます。
これまで、独学および会社の諸先輩方が築き上げた知見・ノウハウに従って斯様な業務を取り進めて参りましたが、「一度自身の理解を体系的に整理し、更に能力を高度化・改善したい」と常々思っておりました。
その中で会社から本セミナーへの参加を打診頂き、参加を決めました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
セミナーはケースメソッドを用いた授業となりますが、ケースでは実際のビジネスの現場で発生する諸問題を具体的に取り上げ、「そのケースの主人公であった場合、その発生した諸問題に対してどのように取り組むか?」という問いに当事者意識を以て分析し、自身の考えを構築していくこととなります。
実際のビジネス現場での経営者・起業家の考えに触れ、これまで確信の持てなかった、論理的な戦略構築や意思決定に向けた基本的な考え方を体系的に学ぶことができました。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
上記のとおり体系的に学んだ知識を業務に落とし込むことは勿論ですが、本セミナーで気付かされたのは「ディスカッションの重要性」です。
セミナーでは期間を通じて、各教授陣および参加者と一日中徹底的に議論を繰り返すことになります。個人予習の時点では「もうこれ以外の考え方や切り口は無いだろう」と思うところまで考えて準備をしていましたが、議論をする中で自分の持てていない切り口や知識が次々と出てくることに改めて気付かされました。自分は井の中の蛙であったと。
これからはマネジメントの立場で業務を遂行していくことが多くなると思いますが、第三者の意見にさらに耳を傾け、様々な意見を広く取り入れるマネジメントを意識していきたいと思います。



第121回経営幹部セミナー
森山 英樹 氏(第121回経営幹部セミナー受講)
JFEエンジニアリング株式会社
プラント建設本部 制御建設ユニット エネルギー制御建設チーム
室長
経営幹部セミナーを受講した目的
私の部署は建設工事の技術部門ということもあり、実務ではマネジメント能力が大きく求められます。一方、マーケティングや経営という視点からビジネスを考える機会は少なく、経験や能力が偏ったものとなっており、バランスの悪さが自身の弱点でもありました。いつかは経営に関して学びたいという思いを抱えていた中、タイミング良く会社からセミナーの参加依頼があり、チャンスという思いと長期滞在型という不安を同時に抱いたのが正直なところです。しかし、集中的に没頭できる環境下であること、他業種の方の考え方を吸収できること、マーケティングや財務諸表など上流概念を学ぶことで自身の固定観念を打破し視野を広げることを狙いとして臨みました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
マーケティング、経営、財務、情報分析、組織マネジメントといった領域を身近なケースでリアルに触れたことで、トップ経営者の思考回路を肌で感じることができました。フォーカスする対象は何か、自分だったらどうするか、その判断能力が自分に備わっているかを常に考え抜くことで自分と真剣に向き合う機会となりました。また、各テーマは関連性があり、大きな輪を持って経営は成立し、バランスが崩れると企業は経営危機に陥るのだということを学びました。クラス討議では、利害は関係無く自由に発言し合い、時には議題から脱線することもありつつ開放的で素直に尊重し合える空間であり、この環境を自社にも展開すべきだという気付きも大きな習得でした。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
今回、私が大切にしていきたいと感じたものは「理念」です。社長、グループ、個人など様々な理念が存在し時には衝突する場面もあると思いますが、本来どうあるべきかを根気よく真剣に考え抜くことを大切にしたいと考えています。また、マネジメントに加えて市場動向や財務諸表の分析といったマーケティングの視点を若いメンバーも意識するよう裾野を広げていくとともに、微弱な市場変化にもアンテナを張り、柔軟で大胆な経営発想ができるよう、今回得たセミナー仲間も含め外部刺激を継続的に取り入れていきます。今後いかに会社に新しい風を吹き込む事ができるか期待をしつつ、このセミナーを契機に経営概念を学び続け業務に活かしていきたいと思います。



第120回経営幹部セミナー
安部井 淳 氏(第120回経営幹部セミナー受講:京都東急ホテル会場)
株式会社デンソー
サーマルシステム事業グループ サーマル先行開発部 総合熱マネ開発室
担当課長
経営幹部セミナーを受講した目的
課長クラスの研修プログラムの一環として受講させていただきました。自動車業界では100年に1度といわれる変革期を迎えた今、マネジメント職として、これまで以上に社会の変化に対する感度を上げ、スピード感をもった企業経営や組織運営が必要になると感じていました。さらに私が所属する先行開発部では、弊社の製品を採用いただく自動車メーカーはもちろんのこと、その自動車を実際に使用するエンドユーザー目線での商品企画にも力を入れています。本セミナーは実在の企業ケースを用いて、総合経営、組織マネジメント、財務管理、マーケティングなど多岐にわたる経営知識が得られると同時に、私が強化したいと考えていた商品企画スキルを身につけるのに大変良い機会であると感じ、参加させていただきました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
ケースを通して学ぶことで、自らがそのケースの中へ疑似的に入り込み、当事者の立場で考え、意思決定し発言することができ、あたかも実体験のように経営知識を体得することができました。教科書で学ぶだけではなくケーススタディに取り組むことのメリットは、自身の経験として深く印象付けられることだと思います。また、様々な業種の方々とのディスカッションを通じて、今までの自分では考えもしなかった視点での意見や判断に触れ、視野を広げることもできました。そんな皆さんと10泊11日にも及ぶ長期間のセミナーを共に乗り越え、切磋琢磨することで、単なる知り合いではなく、戦友になれた気がします。今後も困ったときには互いに相談しあい、業種を超えた議論ができると信じています。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
セミナーでの学びや気づきから、以下の3点を意識し取り組んでいきたいと考えています。一つ目は、CSV(Creating Shared Value):共通価値の創造の観点から、自社の利益だけではなく、本業を通じて社会へ貢献できる長期的構想を描くこと。二つ目は、差別化意識のあまり自社単独の開発に固執するのではなく、その分野を得意とする他社との協業や共創を検討することで、エンドユーザーのニーズにスピード感をもって応えること。三つ目は、エンドユーザーにとっての本当の価値は何かを常に考え、それを提供できるソリューションを具現化することです。このような学びや気づきを職場のメンバーとも共有し、エンドユーザーにとって本当に"嬉しい"ビジネス・製品を創出していきたいと思います。



第64回高等経営学講座
多田 理一郎 氏(第64回高等経営学講座受講)
株式会社肥後銀行 東京支店
本州ブロック統括兼東京支店長
高等経営学講座を受講した目的
業態を超えた競争激化、超低金利政策の継続、新技術の台頭など、銀行を取り巻く経営環境が大きく変化する中、私は組織のリーダーとしての意思決定を合理的かつ納得性の高いものへと変革するためにどのように取り組むべきかを模索していました。そのような中、実践的な経営の意思決定を行う実務能力養成を目的とした「ケースメソッド授業」を通して、混沌とした経営環境の中で主体的に考え結論を出す訓練となる本セミナーを知り、受講を決意しました。私は多くの企業が陥りがちな既成概念のみによる意思決定に常々疑問を感じていたので、正解がない状況下における自由な発想による議論を通した意思決定プロセスを習得することが一番の目的でした。
高等経営学講座で得たもの、学んだもの
総合経営、マーケティング、財務管理、組織マネジメント等、ケースメソッドで取り上げられたテーマは広く、深いものでした。そして事前個人研究⇒グループ・ディスカッション⇒クラス・ディスカッションという授業形態が、自身の理解を深め思考力を大きく鍛えました。一番重要なのが事前個人研究です。中には一度読んでも真意が理解できないケースもありますが、何度も読み直したり側面調査をしたりしながら自分なりの考えを整理することが学びの第一歩となりました。その後、グループやクラスで他の受講生の見解に触れることで、自分の思考はまだ浅く一面的であることを痛感するとともに、企業経営に係る知識や思考力・洞察力など多くの学びを実感できました。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
銀行の支店長として、経営環境の分析やマーケティング戦略の策定、組織マネジメントなどあらゆる分野において、より幅広く深みのある構想力とリーダーシップを発揮していきたいと考えています。いま私が行動すべきことは、目先の事象への対応や利益追求ではなく、持続可能な事業モデルの構築と豊かな地域社会の実現への貢献です。従来の経験則からは導き出せない大きな課題であるがゆえに、本セミナーで学んだ自由で幅広く深い構想力と意思決定力を十分に発揮し、道なき道を開拓していきたいと考えています。また、ケースメソッドで学んだ考え方の本質を職場のメンバーひとりひとりと共有することにより、組織的な課題解決力の向上を目指します。

第64回高等経営学講座
山本 周子 氏(第64回高等経営学講座受講)
株式会社野村総合研究所
クラウドサービス開発一部 部長
高等経営学講座を受講した目的
担当事業の戦略を考える場面で、直面する課題の打ち手には自信があっても、中期・長期の成長戦略としての視点の置き換えに苦戦し、悩むことが多々ありました。そのような折、自社の研修プログラムの一環でこの講座を紹介されました。2019年度テーマである「拡がる競争、拡がるマネジメント」はクラウドを扱う自分にとって強く魅かれるキーワードであり、トップとしてのビジョンと戦略の再構想を目指したカリキュラムは自身の悩みの解決の糸口になると直感し、受講を決めました。また、変化の激しい経営環境に身を置かれている他社、他業種のリーダーの方たちとのコミュニケーションを通じて、様々な思考や意思決定のプロセスに触れられることも大きな期待でした。
高等経営学講座で得たもの、学んだもの
全てのケースに学びがありました。リスクマネジメントや組織マネジメントのような比較的経験のある分野では、新しい知見だけでなく、過去の知見を再整理し、体系的に理解しなおすことができました。M&AやCSRを扱ったケースでは、ディスカッションを通じて経営トップの思考や意思決定のプロセスをトレースしたことが、新しい視点・視座の擬似体験となり、間接的に自社のトップマネジメントに対するより深い理解が促されたと感じました。SDGsについて考える時間をこの時期に持てたことも有益でした。また、一般消費者向けビジネスに縁の無い自分が、購買行動類型を面白いと感じ、マーケティングに関心を持てたことは、異業種の受講生が集まるこの講座ならではの成果です。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
経営に関する幅広い分野を専門分野の教授や様々な業種の方たちと集中的に学んだことで、自分に無かった考え方や課題解決のヒントを多数得ることができました。今後、それらを意識して応用し、引き出しを増やすことにつなげていきたいと考えています。そのような学びの活用に加え、「多角的な討議」の活用についても強く意識しています。予備知識の不足から不安を抱えて臨んだ授業において、ディスカッションを重ねるうちに、自分の内に自然と意見が芽生えた感覚を、組織の運営に応用したいと強く思います。課題の共有、自立した思考、相互の理解と尊重を前提とした活発な意見交換ができる組織作りを目標に、今回の経験を活かした行動を始めたいと思います。

2018年度週末集中セミナー
若杉 司氏(2019年3月 全8コース修了)
株式会社マルタケ
代表取締役副社長
一昨年4月より経営者としてのポジションとなったものの、その経営者というポジションからの思考や経験値等において明確な根拠・自信のある思想を持ち合わせておりませんでした。
慶應義塾大学ビジネス・スクール主催のセミナーへの受講を弊社代表から示唆、協力いただき、経営者としての修練、啓発、またこれから協力して社の経営を進めていく人材間の共通言語を習得すべく、弊社社員2名とともに受講することとなりました。
2年間にわたるセミナーでのさまざまな業種・パーソナリティを持つ方々との思考交換や刺激受けたこと、相互研鑽により、新たな思考の発見や自身の思想の確認といった貴重な財産を得ることができました。
『「思い」偏重』という自身のポリシーは決して悪いわけではなく、経営判断において「思い」は不可欠であると同時に、そこにはやはり「根拠」という目線が重要だということをあらためて感じることができました。この心・脳・身体に「シャワー」として浴びた経験は、これからの「ありたき姿」への大きな糧となることと信じています。貴重な時間を共有させていただいたみなさまには大変感謝しております。
約束された正解のない、現実社会へ、ケースメソッドによる学びをいかすと同時に継続的施行で挑んでいきます。



2018年度週末集中セミナー
居城 洋氏(2019年3月 全8コース修了)
株式会社マルタケ
経理部 課長
今回、弊社社長の薦めにより本セミナーを受講しました。
ケースメソッドは実際に企業で起きた事象であるため、具体的なイメージを身近に持つことができ、大変興味深く、当事者目線を持って取り組むことができました。セミナーを通じて、企業において発生する様々な課題に対する見方、考え方、分析手法を学ぶことができました。
直面する課題の背景にある種々の原因を探すこと。一つ一つの原因に対し、解決策、方向性を見出し、向き合うこと。この流れを、ケースを通じて幾度となく繰り返すことで、体系と理論の両輪で学ぶことができました。
また、学んだケースを自社の抱える課題に置き換えて考えることで、学んだ内容を、より実践的な目線で捉えることができました。自社の目線で向き合うことで、今後の自社課題に対する見方、取り組み方のヒントを得ることができました。セミナーを通じて得た大きな収穫でした。
グループディスカッションを起点にした形式も刺激になりました。ディスカッションに向け、自身の考え方を明確にしておく必要があり、多くの時間を予習時間に割き、共に参加した自社メンバー内でも事前共有を行ってきました。この過程で団結力が深まり、お互いの考え方、価値観など相互理解が深まりました。今後、共に進んでいくうえで、とても貴重な時間であったと感じています。
今後は、セミナーを通じて得た財産を積極的に自社に還元すべく、チーム一丸となって取り組んでいきます。



2018年度週末集中セミナー
茂木 稔之氏(2019年3月 全8コース修了)
株式会社マルタケ
執行役員営業本部長 マーケティング担当
私は今回初めてKBSでケースメソッド方式による学びを経験しました。最初は慣れない横文字のキーワードが多く、自分の知識不足を痛感しました。グループ討議では、普段の業務ではなかなかお会いできない、多様なバックグランドを持つ方々と意見交換をして、様々な考え方に気付かされ、それはとても刺激的で、自分自身の考えをブラッシュアップさせる事ができました。その後のクラス討議では、ディスカッションをする人数が増え、より多様な参加者による、より深い議論へと進み、自分が発言することを通じて多くを学ぶ事ができました。
【2年間全8コース】のケースメソッド方式による学びは私にとって得るものが非常に大きく、これからのビジネスに役立つことと確信しております。特に意思決定においては、過去の経験・勘・勢いに頼って判断していたことがありましたが、各講座を通じて学んだ事により、問題解決に対しての合理的判断に基づいた意思決定・顕在化されていない問題点の発見など実務能力の向上・ビジネスで最も重要なスピード感のある判断力を養うことができたと思います。全講座を通じて人脈を広げられた事に感謝いたします。
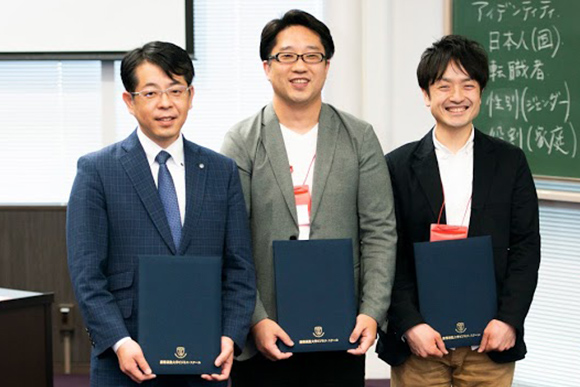


第119回経営幹部セミナー
近藤 佳介 氏(第119回経営幹部セミナー受講:伊豆今井浜東急ホテル会場)
株式会社守谷商会 機械2部2課 課長
経営幹部セミナーを受講した目的
自社の研修プログラムの一環として参加しました。
①これからのビジネスリーダーに求められる経営基礎知識、問題発見・解決能力、コミュニケーション力、特にスピード感のある判断力を養うこと。②慶應型ケースメソッドという一般的な知識や理論の一方向講義からは得られない、双方向の講義による実践的な学びを得ること。③異業種・異職種の受講生と積極的にコミュニケーションを図り、多角的な視野を身につけること。
これら3点を大きな目的として受講しました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
各ケース、全てにおいて得たもの・学んだものが沢山ありました。財務・管理会計・組織マネジメントといった経営に必要な基礎知識はもちろんのこと、市場環境の変化や将来の競争を見据えた経営戦略・マーケティングについても多くの学びがありました。直面する課題に対し、ケースメソッドではその場で何を感じ、何を考え、何を受発信するか、これら全てがライブであり、ビジネスにおいて最も重要だと考えるスピード感のある判断力を養うことができたと思います。11日間を通して、異業種・異職種の方々と年齢・役職・立場を問わず、同じ土俵でディスカッションできたことは本当に貴重な経験であり、このセミナーでないと得られない刺激を受ける事ができたと感じています。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
異業種・異職種の方々とのディスカッションを通して、自分では思いもよらない発想を得られることを体感しました。ケースはあくまでケースですが、扱われている業界・業種は多岐に渡り、企業が直面する課題や経営危機に対し、自らがその企業の経営者として、分析・評価・意思決定をする体験ができたことは今後の職務で生かせる学びを得られたと考えています。今、目の前にある課題だけでなく、顧客ニーズや市場環境の変化を敏感に感じ取り、将来の競争に勝つため、今回のセミナーで学んだことを生かしていきたいと思います。また、一人でできることは限られており、仲間と志を共にして取り組むことで、セミナー中のディスカッションのような相乗効果が得られると思いますので、今のチームの関係性を高めて結果の質を追い求めていきたいと思います。





第119回経営幹部セミナー
柿原 督史 氏(第119回経営幹部セミナー受講:下田東急ホテル会場)
住友生命保険相互会社 営業人事部 部長
経営幹部セミナーを受講した経緯や今回の受講での学びの目的
会社から、「合宿形式で10泊11日」という長期間のセミナーだが、有意義なセミナーなので出席してはどうかという打診があり申込みをしたというのが正直なところです。そのため、日程が近づくにつれ、目の前の仕事のことが気になり始め、少々後悔をしていました。
ところが、セミナーの始まる3週間ほど前に、事前課題やカリキュラムが手元に届けられ、セミナー受講に対する自分自身の姿勢が大きく変わってきました。
理由は3点です。
10泊11日間という長期間仕事をほぼ完全に離れることで、
① これまで積み上げてきた経験・知識を、実際に起きたビジネスの実例から体系的に見ることで、これまでの経験・知識の振り返りになるのではないか
② 今後の経験自体がより具体的な大きな学びになっていくのではないか
③ 自身の強みを伸ばし、弱みの底上げを図ることになり、今後のキャリアがより充実したものになるのではないか
このような期待と目的をもってセミナーに臨みました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
各講義の内容は、マーケティング、組織マネジメント、財務管理、会計管理等々のテーマで、国内外で実際に起こった事例が多岐にわたって用いられています。事例によっては、ニュースとしてただ漫然と見ていた事例もありましたし、これまでの経験・知識では全く太刀打ちしようのないテーマもありました。
ただ、いずれの事例においても、事例を読み込み、グループで議論し、クラスで深堀りしていく過程において、様々な業種・職種、年齢、そしてバックボーンの異なる方々と議論することは、自らの強み・弱みを知るとともに、同じ事例についても様々な受け止め方・考え方があることを改めて感じることができ、大きな発見となりました。
そして何よりも、11日間という長期にわたり共にグループやクラスで議論した受講者の皆さんともいい関係を築くことができ、今後の社会人としてのネットワークも築くことができたと思います。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
日常の業務においては、常に判断を求められます。当然、目の前の事象を乗り切ることは大切ですが、その判断は現状をよく認識し、将来を見据えた判断でなくてはなりません。
今回のセミナーで学んだ事例においては、数多くの経営判断が盛り込まれ、その背景には経営理念が大きな存在となっていました。私の勤務する住友生命にも「経営の要旨」という企業理念があります。
企業理念を大切にし、長期的な視点に立って一日一日を大切に過ごすこと、それが仕事にやりがいを感じ、そしてそれが生きがいにも通じていく、そしてそれが同時にお客さまのためになり、会社の繁栄につながっていくのだと改めて感じています。
今回のセミナーを通じて、経営者の視点に軸をあげた考え方を学ぶとともに、自分自身の強み・弱みを認識することができたと感じています。今回のセミナーで感じたこと・学んだことすべてを大切に、より充実した毎日を送っていきたいと思います。





第118回経営幹部セミナー
本多 洋介 氏(第118回経営幹部セミナー受講)
株式会社サーラコーポレーションマーケティング部
経営幹部セミナーを受講した目的
所属企業グループでは幹部候補生に対し「次世代経営人材育成プログラム」が用意されており、その中に本セミナーがあります。現在、新規事業開発責任者と宅配水事業会社経営責任者を任されており、日々「意思決定」の連続に直面する中で、「経営」に必要な要素や体系立てた思考・判断の組み立て方を学びたい欲求があり、今回の受講を決めました。
決め手は、実際の事例に基づき自身が真剣に考察や思考を重ねつつ、並行して他業種で活躍されている方々との本気の討議を経て意思決定力や問題解決能力を磨く「ケースメソッド」という学び方でした。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
「経営者」の視点で「マーケティング」「財務会計」「組織マネジメント」等8つのテーマが輻輳する実例をいくつも疑似体験する中で、経営は真の総合的判断の繰り返しであることをダイナミックに実感しました。
他方、経験豊富な他業種の方々とのグループ討議や先生方の講義を受ける中で視点の偏りや視座の低さ、思考の浅さ、判断の選択肢の少なさを痛感し「未熟な自分」と向き合うことにもなりました。
特に苦手な財務戦略においては投資や資金調達など丁寧に検討すること、他方、企業が得たい価値から大局的に手を打つといった、相反する視点で事案を最終的に意思決定していく「経営の胆力」を感じたことが鮮烈な「発見」となりました。出会った仲間とはグループ討議だけでなく、食事等で様々な意見交換することができ、苦しいながらも楽しい時間を過ごせたことも「価値」です。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
今回、経営者になるための「種まき」をしました。日々の業務執行の中での判断・意思決定を行う中で、まいた「種」を大きく育てていきます。現在携わっている新規事業開発には今回学んだマーケティングや財務戦略、組織マネジメントのあらゆることが関わり、最終的には事業性の評価や意思決定をしていかないといけません。私より年齢の若い、次世代を担う層を巻き込みながら、今回の学びの「種」の拡散をしていきたいと思います。
人口減や高齢社会、労働力不足や市場の成熟・縮小など「変化」や「問題」は、むしろ都市部より地方の方が早く顕在化します。企業経営を行う環境も劇的に変化していくことでしょう。その変化にも正面から向き合っていきたいと思います。



第63回高等経営学講座
木村 健一郎 氏(第63回高等経営学講座受講)
大同特殊鋼株式会社
高等経営学講座を受講した目的
私が勤める大同特殊鋼株式会社はB to Bの典型的な企業です。現在、自動車業界を中心に顧客のビジネス環境は激変している状況にあります。変化が叫ばれる中で経営における一通りの意思決定のプロセスに関して自分には何が足りないのか、どのような考え方を習得すべきかを探索していました。本セミナーの受講者は業界が多岐に渡っており、職務も技術系と事務系がほぼバランスされており、職位もほぼ自分と同位であったこと、また9日間の集中開催であることから、日々の業務と完全に切り離し業界や社内の慣習や常識にとらわれる事なく純粋な学問として勉強しようと思い、受講を決めました。
高等経営学講座で得たもの、学んだもの
ケーススタディにおいて得意、不得意な領域があったのは事実です。最初は議論が発散しがちになりますが、考え方に関してはほぼ同じ方向に向かう傾向がありました。しかしその後の講師を交えての討論では思わぬ展開が起こることもあり、一つ上の層での考え方を学ぶことができました。事前学習でまとまった自分の考えがグループ討論で修正、肉付けされ、講師との討論で洗練されることもありましたし、崩壊することもありました。日頃、社内の業務においてはなかなか出てこない発想や切り口は参考になりましたし、何よりも全てのケースにおいて、「意思決定の絶対的な正解はない」ということは大いに勉強になりました。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
今回、数々のケースを経験しました。私の業界に関するケースはゼロでしたが、自社に置き換えて考えると共通な考え方ができる場面は多数ありました。今後は多様な企業についての研究をしながら自社の課題解決を推進していきたいと思います。得意な分野でも考え方や意思決定を決め付けず、不得意や専門でない分野においても基本的な意思決定における考え方は大きく変わらないという気付きがありましたので、何事にも積極的に関与していくことを念頭において企業人として成長できるように努めていきたいと思います。

第63回高等経営学講座
木川 真希子 氏(第63回高等経営学講座受講)
株式会社集英社 常勤監査役
高等経営学講座を受講した目的
ビジネス環境の変化が激しい中にあって、監査役として、「会社と人が元気になるような仕事で貢献したい。でもどうやって?」 そのヒントを求めて参加しました。
第63回のテーマ『新しい技術、新しい市場』が、今一番興味がある分野だったことにも強くひかれました。また、実在の企業に起こった事象のケースをもとにディスカッションで学びを深めていく授業は、力がつくと実感しており、そのスタイルが好きだったこと。カリキュラムに、ビジネスの全体を理解するために必要な財務会計、組織マネジメントなどの要素がバランスよく含まれており、自分がこれまでばらばらに学んできた要素を、点検、補強するのにちょうどよかったこと。そして講師、受講生の方々との出会い。未知の分野のどんな面白い話が聞けるかという期待。実は、それが最大の狙いだったかもしれません。
高等経営学講座で得たもの、学んだもの
Google、Amazonなどの最新のケースが多かったので発見の連続でした。特に、ハーバードビジネス・スクール Pisano教授による、アメリカの「バイオベンチャー会社を育てる会社」の事例は、夢をビジネスに育てていく内幕を垣間見ることができ、エキサイティングでした。多くの成功事例で共通して感じたのは、アイデア出しにおいては「自由」が決定的な影響を持つことです。自由で安心できる空気が心を伸びやかにし、それが豊かな発想、斬新なアイデアにつながる。そのうえで厳しい圧をかけてビジネス化に向けて絞り込む。そのメリハリは大きな発見でした。
授業はスリリングで、講師に意外なところから突っ込まれ、面食らう場面も多々。でも、毎日揺さぶられるうちに、正解か否かではなく、自分がどう考えるかが問われていると感じ始め、固まった心と頭が少しずつ自由になっていくようでうれしかったです。
受講生には、中国やインドなど海外でトップを経験した方も多く、腹のすわった考え方に、セミナー冒頭で取り上げられた「視座」(大局観)の身近な例を見る思いでした。幅広く刺激的な出会いは、特に、トップを目指す女性にとって得るものが多いのではないかと思います。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
「新しい技術、新しい市場」を生き延びた会社は、クリエイターをクリエイティブな仕事に専念させ、さらに思い込みの暴走を防ぐ仕組み、そして、失敗からビジネスを生む仕組みづくりに優れています。そのアイデアを生かし、会社の元気につなげたいです。

2017年度週末集中セミナー
大槻 俊輔氏(2018年3月 全8コース修了)
学校法人近畿大学
医学部附属病院脳卒中センター
学問はひとや社会を豊かで幸せなものにするためにある。我が国では、学問は志があれば平等に受けることができる。私は神経救急医療の最前線で高度に進歩してきた医学を駆使して社会に貢献してきたが、時に医療は社会の経済や政治に大きく影響を受けてきた。経済や経営について学びたくなった。だから気楽にまずは一科目、そして次も。結局一気通貫となりました。
ケースメソッド方式という予習、現場人とグループ議論、そして教員からの講義とクラス議論、帰路での振り返りが一連のスクールです。力を得て書籍に当たり1、2ヶ月咀嚼、実務に十分消化した上でフィードバックさせました。講義は日々の実務で胸にあった「もやもや」とした疑問や悩みを吹き飛ばすこともなく、答えを教えることもありません。さまざまな事例を一般化して、どのような考え方で決断をして、方策を立て実行、評価をする「なんとか対処する力strength to manage and survive」を教えます。個性あふれる教員からの難解な質疑に多種多様の回答、科学的かつ謙虚に、時にご自身の大胆な含蓄する解説、朝焼けの富士山見える協生館および週末サバティカルへの職場の援助に感謝しております。

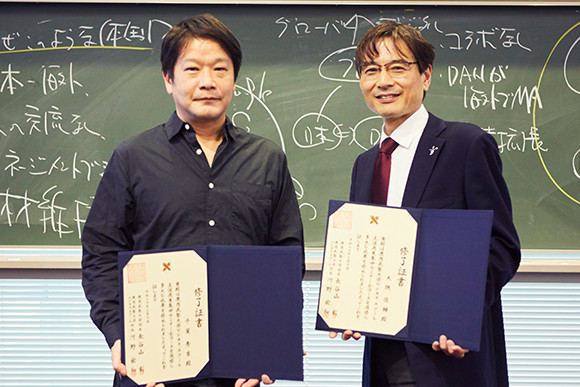
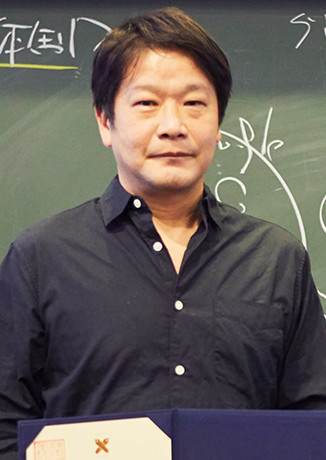
2017年度週末集中セミナー
千葉 秀吉 氏(2018年3月 全8コース修了)
マニュライフ生命保険株式会社
新事業企画開発部 法人推進グループ マネージャー
以前よりビジネススクールで実践的な経営学を学んでみたいと思っておりました。ビジネスの世界では経験と勘に頼る部分はありますが、体系化された知識と実際にあった企業のケーススタディを学ぶことで、実務面で合理的な判断や、多様化した様々な問題解決に生かすことができると思い、勤務先の人材教育プログラムに応募し、参加するチャンスをいただきました。
2年間、8コースの受講でMBAのエッセンスを学ぶことできます。テキストを事前に読み、設問に沿って自らの考え方を整理して授業に臨むため、平日は移動中や隙間時間に勉強することとなり、大変でしたが、充実した毎日を送ることができました。
企業の法人推進を担当しておりますので、経営者とお会いする機会も多く、本セミナーで学んだ知識や経営的判断についてアドバイスさせていただくこともあり、大いに役に立っております。また社内研修では講師として話す機会もありますので、今後も知識を活用していきたいと思います。

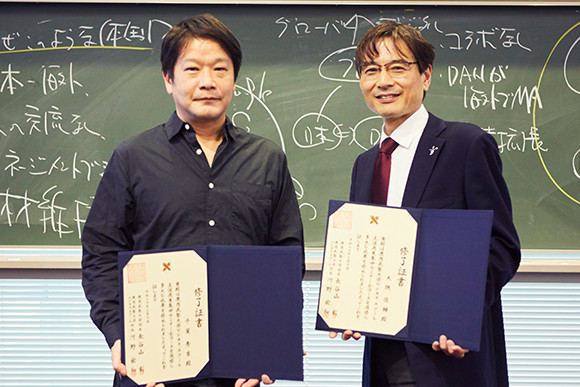

第117回経営幹部セミナー
四方田 美穂 氏(第117回経営幹部セミナー受講)
株式会社ローソン ローソン大学
経営幹部セミナーを受講した目的
組織の幹部となる人材は全社的且つ総合的に事象を判断する力を持つことが求められます。早い段階からその能力を養う訓練を繰返し行う事が、未来の組織成長に繋がると考えています。
今回のセミナーは
1)実例のケースから経営に関するさまざまな分野を横断的に学ぶこと。
2)様々な業界から参加される実務経験・知見が豊富な方々と議論を深めることで、異業種や他者の
物の考え方や意思決定方法の違い等を確認し、今後の自身や自組織の成長に活かすこと。
の2点を目的に受講いたしました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
各講義に学習テーマがありましたが、研究の中でケースの背景に、財務会計・マーケティング・組織マネジメントといった経営要素が存在していることがよく理解できました。「意思決定は真に総合的に行われ、また行われるべきものである」ということに気づけたことは今回のセミナーで一番大きな学びです。
また、全く業種の違う企業のケースが多くあり、他業界の歴史や企業理念、財務状況などを知る良い機会になりました。また個人研究で行った分析プロセスが、受講者の所属する企業や職務によって違っていたことが非常に興味深い点でした。それはグループやクラス討議での議論が白熱する理由となるとともに、そのような観点の違う意見をどのように自身で受け取り理解するのか?自分の組織でこのような多面思考を出せる環境を創るためにはどうすればよいのか?といった自身や部署内での課題に気づくことに繋がりました。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
まずは部署内での財務会計管理・組織管理において、広義を意識した意思決定を心掛けることで学びを実にすると共に、業務である研修では、今回学んだ要素を少しでも研修対象の事業経営者へ共有できるよう工夫していきます。
また、今後の自身・企業成長のためにという点では、経営の基本的知識の理解を更に深め、今セミナーで交流できた方々との情報交換等を通じて応用能力を高めたいと考えています。

新たな視座・視野・視点に気づかされた

すばらしい仲間と再会を誓った
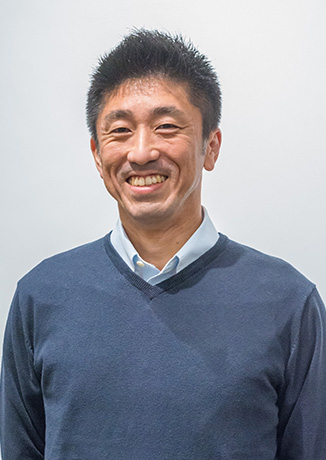
第117回経営幹部セミナー
本田 隆彦 氏(第117回経営幹部セミナー受講)
東芝テック株式会社 リテール海外事業推進部
経営幹部セミナーを受講した目的
経営を担っていく上で習得すべき幅広い分野の知識を、実際の事例に基づいたケースメソッドにて議論中心に学んでいくことに魅力を感じ受講させていただきました。
また、日々の業務から離れ、10泊11日もの間、集中して勉強に没頭できるということ、様々な業界・職種出身で次代のリーダーと目される方々と密度の濃い時間を共に過ごすことを通じて新たな知見を得、自身の成長に繋げられるのではないかという期待もあり、参加させていただきました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
実際の経営における意思決定の場面では、不十分な情報の中で、理論と自身の経験を十二分に駆使して、決断を繰り返していくということが求められていると理解しております。
ケースに記載されている範囲の限られた情報と1ケースあたり数時間程度の自己学習・準備、それに続くグループディスカッションという限られた時間の制約の中で、ケース当事者の立場で擬似、意思決定を繰り返し行うという体験は、課題解決に向けたアプローチの訓練、考え方についての理解の深化において非常に有意義なものでした。合わせて、意思決定に至るプロセスを補助するものとしての様々な理論・フレームワークも学ぶことができました。
これらの理論については、今後自主学習により理解をより深めていきたいと考えています。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
研修で学んだものを、直ぐにそのまま活かせるという場面は、それ程多くはないのと思いますが、日々の業務においても常に経営者の高い視点をもって、内に経営者としての意思決定を行うつもりで、本研修で学んだ課題解決のアプローチ・考え方を応用していくということを意識しながら職務にあたっていきたいと思います。



第116回経営幹部セミナー
堀内 昭宏 氏(第116回経営幹部セミナー受講)
伊藤忠商事株式会社 金属カンパニー金属情報化推進室
経営幹部セミナーを受講した目的
弊社ではマネージャーになると同時に短期MBAの取得が必須となっております。経営の基礎を学習するにあたり、単なるインプット型の研修ではなく、実際のケースに対して、自分の経験を踏まえて他業種の方と議論を深めてアウトプットしていく"ケースメソッド授業"が、今後の自分のキャリアや実務面で大きなメリットとなると考え受講しました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
普段は「経営の基本的な知識」と言われてもピンとこないかもしれません。本セミナーでは各ケースに対してマーケティングや会計管理など、それぞれの分野別に分析しますが、実際に起こったこと(起きていること)が題材となっており、リアリティのある学びができました。また他業種の方の様々な視点でのアプローチにより、自分では思いもよらない意見や判断について考えさせられ、常に視野を広く持ち多方面から物事を分析する姿勢の大切さに改めて気付かされました。11日間という長期を共にグループやクラスで議論した受講者の皆様ともすっかり級友となり、今後の社会人として有効なネットワークも築けたと思います。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
実務上の課題や戦略を考える際に、本セミナーで学んだケースや視点などを活用し、実践していきます。また自分の部署のことだけでなく、「他部署ではどうなのか?」「自社の方向性は?」など、広い視野で業務にあたることで自身の業務に対するプレゼンスを引き上げていきたいと思っています。

第116回経営幹部セミナー
山本 朋美 氏(第116回経営幹部セミナー受講)
倉敷化工株式会社 品質保証部
経営幹部セミナーを受講した目的
組織マネジメント、財務管理等、経営を担う人材に必要な基本知識を網羅した様々な事例を題材に学び、応用能力向上を図ることと今後本業で活かせる論理的手法を得ることが大きな目的でした。今回、弊社からは、開発課、法務課、品質保証課から3名参加しました。会社の狙いとしては中堅社員を対象に幹部社員に必要な資質の早期育成を目的としており、早い段階から、自部門に偏った考えではなく全体最適を常に念頭に置いて業務に取り組むことが期待されています。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
国内外、多岐に渡る業界の実際に起こった事例(ケース)が用いられていることにより、グループ内で真に迫った議論ができ、幅広い年代・業種の方々と一緒に議論することで自分には無い発想を得、学ぶことが多く、複数人で問題解決に取り組む楽しさと難しさの両方を体験できました。時代背景、会社の規模、理念、立地等全ての要素を考慮した上で、なぜそのような意思決定がされたか経営者の思考をなぞり、また、自分ならどう意思決定するかを考えることはとても良い訓練になりました。変動の大きい世界動向に対し経営戦略を立てる時、置かれた環境や立場で目指すべき方向性は大きく変わってきます。変化を恐れず、会社のポリシーが顧客の求めるものと合っているかどうか定期的に見直すこと、信頼を持てる仲間を見つけること、失敗をした時には素直に素早く是正に取り掛かること等の重要性を学びました。財務諸表を見る場合にも、業種によって特徴に違いがあり、また同業種であっても目的が変われば構成が変わってきます。経営は数字が全てと言われますが、数字に惑わされることもあるという、そういった視点も研修中の面白い発見でした。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
私は現在、品質に関わる仕事に携わっておりますが、日本が品質と技術で世界をリードしてきた時代は終わり、顧客のニーズが変化している中で、過去の栄光に固執したまま時代に取り残されないよう、うまく舵取りをしていかなければならないと感じています。品質は良くて当たり前の現代、過剰品質になる一歩手前のどこで落とし込みをするか、また海外展開が拡大していく中で、いかにマザー工場主導によるグループ全体での同品質・同体質を実現していくかが課題であり、今回の学びを活かし柔軟な広い視野を持って会社全体の活性化の起点となる品質マネジメントを行っていきたいと思っています。

第62回高等経営学講座
寺嶋 克知 氏(第62回高等経営学講座受講)
ギガフォトン株式会社 経営企画部 副部長
高等経営学講座を受講した目的
ギガフォトンでは、最先端の半導体生産に使われる露光装置のキーコンポーネントであるエキシマレーザの開発・生産・販売・サポートを行っています。半導体は、IoT・自動運転・AI等によって今後も需要が増加する見込みで、市場が拡大していく産業と言われています。その一方、当社の顧客である半導体メーカーの寡占化は急激に進んでおり、決して日々穏やかにできる状況にありません。このような環境の中、半導体以外の分野の新しい市場を開拓することが当社のさらなる成長のための課題となっており、本講座にて何かヒントになるようなものを得たいと考え参加しました。
高等経営学講座で得たもの、学んだもの
外部と遮断された環境で、短期間に多種多様なケースを個人学習、グループ・ディスカッション、クラス・ディスカッションの3段階で行うことにより、自分だけでは思いつかない視点・視野・視座に触れることができました。特にグループ・ディスカッションでは、少人数だったこともあり、活発な議論が交わされ、時にケースから大きく脱線した議論になりながらも、各自の業界・経験等に基づいた意見が多く出され、日々の業務ではできない貴重な体験をすることができました。また、ディスカッションの合間に設けられた体操の時間は、タフなスケジュールを一瞬忘れることができ、これは普段の業務でも適当な気分転換が必要だとのKBSからの教えであったのかと後で気が付かされました。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
それぞれのケースについて、「当社に置き換えたとするとどのようになるのか?どうすべきなのか?」などと考えながら本講座を受けていましたが、正直に言うと職務に直接すぐに活かせそうなものはなかなか見つけることはできず、まだ模索中です。ただ、本講座で得ることができた多様な視点・視野・視座で物事を見ることと、受講者・教員・事務局の方々との人脈については今後のどのような業務にも活かせると思っています。あと、もちろんディスカッションの合間の体操もです。

第62回高等経営学講座
中林 真太郎 氏(第62回高等経営学講座受講)
日本オラクル株式会社 社長室
高等経営学講座を受講した目的
様々な業界から参加される実務経験豊富な受講者同士のグループ・ディスカッションや、インタラクティブに展開される活発な講義を通し、企業の成長と変化に対応する知識や感性を成長させたいと思い、受講を決めました。年齢や性別、国籍などの違いはもちろんのこと、異なる業界に属し、多くの成果をあげられてきた受講者から伺う実体験に基づいた意見や、最先端の研究を行っているKBS教員からの講義が、受講者全員に新しいパースペクティブを多くもたらすであろうことに加えて、日々の業務から離れた場所で、学びや感動を共有する時間が非常に多く設けられた当該講座は、学びの場として大変魅力的だろうと思った点も受講理由の1つです。
高等経営学講座で得たもの、学んだもの
期間中、戦略的思考が必要な問いが多く出ました。「この製品の場合、後発で市場参入するか、先発で市場にのりこむか?」、「市場の状況を加味し、あなたならこの商品にいくらの値段を付けるか?」、「一見成功したかのようなビジネスモデルが下降傾向。どのような欠陥が裏に内在していたのか?」、「米国ではデジタル技術を使ったイノベーションが多く生み出されているが、どのような視座から生まれてくるのか?」など、実務経験豊富な事業戦略担当者でも回答が難しい問いを通し、受講者全員が当事者として決断するため、回答を模索しました。過去の経験と勘に頼るだけではなく、一歩ひいて思考し、多面的要素を意識しながら、模範解答のない自分自身の回答を導きだしていきました。企業経営に近いポジションを経験する人々にとって、「どのような知識とメンタリティで目の前の事業課題に取り組み、そして後任を育成していくべききか?」という点において、非常に示唆に富んだ8泊9日だったと思います。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
大事だと感じた内容を、自分なりの言葉や資料にし、具体的な業務シーンの中で社員に伝えていくことが重要だと考えています。また、高等経営学講座で構築できたネットワークを維持し、より良い社会を作るために企業人がすべきことをテーマに、情報交換を行い自ら学び、感じることを絶やさないよう心掛けていきたいと考えています。

2017年度週末集中セミナー
安藤 真理 氏(2017年度週末集中セミナー 会計管理集中コース受講)
穂山興産株式会社
代表取締役
学生時代にゼミで業種別企業研究を経験し、当時からビジネス・スクールで学ぶ機会を得たいと考えておりました。しかし卒業後、そのような機会に恵まれないまま日々は過ぎ諦めておりました。たまたま友人が週末集中セミナーを受講したと聞き、わたくしの心の中に閉じ込めてあった想いが再燃し、「今更受講して何の意義がある?」と自問自答を繰り返しつつも、「結論は受講してから考えよう。」と参加を決意しました。
会計管理集中コースでは、予習に時間をかけた割には手法を間違えたり、計算式を間違えたりして冷や汗をかきましたが、幅広い受講者層を考慮した先生の丁寧な解説に助けられ、理解を深める事ができました。
講義形式ではなく、討論形式の授業のため、企業で日々実践されている他の参加者の皆様の現場感覚に基づき、かつ経営者視点のあるご意見には、大変刺激を受け励みとなりました。最新のデータを使ったケーススタディは臨場感があり、多種多様な分野を対象に幅広く考える良い機会であり、参加者の皆様の実際の感触も加えて一層議論を深める場となることも魅力の一つと感じました。
全8コースですので自身の研鑽に他のコースも検討致しております。

2017年度週末集中セミナー
居城 洋 氏(2017年度週末集中セミナー 会計管理集中コース受講)
株式会社マルタケ
経理部 課長
今回弊社からは、副社長、営業本部長、私の3名チームで週末集中セミナーを受講しました。
会計は会社経営をしていく上で欠かすことのできないものです。ただ、実際のところ、その知識は一朝一夕で身に付くものではありません。週末集中セミナーは、初心者でもこの会計の知識を効率よくしっかりと理解でき、また、実践レベルまで引き上げてくれるものであったと実感しています。まず、「比例縮尺財務諸表」などを通じて、財務諸表の性質、問題の発見方法など、財務諸表から企業経営の本質を見抜く力を学びます。次に、実在する企業のケースについて、グループディスカッションなどを通じ、各人の考え方をブラッシュアップすることで理解の幅を格段に広げることができます。
私は、セミナーをチームで受講したことにより、経営(会計)に対し、共通の「言語」、「指標」を共有できたことに大きな意義を感じています。これは、講義に向けたチーム内での勉強会、そして、素晴らしい先生方からのご指導を共有することで自然と培われていきました。
経営は1人ではできません。経営に携わるチームが一丸となって、目指すゴールに向け、意識を共有し、進んでいくことが大切です。セミナーを通じ、チーム内の共通の「言語」、「指標」を得ることができたことは非常に大きな財産です。

第115回経営幹部セミナー
異業種・異職種の受講生とのディスカッションは自分自身の視点を広げていく
山室 元広 氏(第115回経営幹部セミナー受講)
株式会社デンソー
第115回経営幹部セミナーを受講した目的
所属企業の研修プログラムの一環として受講をさせて頂きました。経営に関する様々な分野を実際の事例に基づく臨場感あふれるテーマで、第一線で働く異業種の受講者たちが議論を中心に疑似体験できるケースメソッドという進め方に魅力を感じ、参加を決めました。
今回のセミナーで得たもの、学んだもの
ケースの当事者の立場であったらどう判断するのか。自らをケースの主人公に置き換え取り組むことにより、各ケースのディスカッションの中から自身の職務にも共通する課題解決方法、考え方といったエッセンスを体感することができました。自らの職務と同一の課題・状況は存在しませんが、自社・自身の課題とどのように関連付けていくのかという視点自体も、本セミナーにおける学びの一つとなりました。
合宿型(10泊11日)セミナーを体験した感想。合宿型セミナーでよかったと思うこと。
仕事・家庭から離れ、集中してケースへ向き合う合宿型セミナーの環境は、受講内容をより有意義なものにすると感じました。また、合宿形式が、異業種・異職種の受講者で構成されるメンバーの関係を深くし、密度の濃い議論を促す重要な要素になっていたと実感しております。
異業種、異職種交流について
企業文化や職種・職務といった背景が異なる参加者が一つのテーマに向き合うことで、課題が多角的に捉えられ、自分自身の視点が知らず知らずのうちに画一的な価値観に陥りがちであったことを痛感しました。研修期間を通して、グループディスカッションの中で繰り返し自分自身の視点を広げていく作業が行えることが異業種、異職種交流の大きな魅力と感じました。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか
セミナーでは、経営全般の分野をケースメソッドという疑似体験を通じ、多くの課題解決のヒント、考え方を体感することができたと感じています。今回の学びを自分自身なりに咀嚼し、セミナーにおけるケースとの類似点を意識しながら職務にあたることで、本当の意味での「力」に変えていけるものと考えています。

第61回高等経営学講座
第61回高等経営学講座に参加して
金川 宏美 氏(第61回高等経営学講座受講)
セイコーホールディングス株式会社 取締役
高等経営学講座を受講した目的 セイコーウオッチ株式会社で執行役員を2年間務めたのちに、6月に親会社セイコーホールディングス株式会社の取締役に就任しました。ウォッチ事業でのマーケティング・商品企画・営業経験をベースに今後はより広範な視点を持ち、グループ会社全体を包括的にマネージメントしていく力量が問われています。事業を取り巻く経済環境は常に変化していき、またそのスピードはグローバル規模で年々早まっていっています。そういった激動のビジネス環境の中で、他企業の経営者がどのような経営戦略を持ち、どういった手法で戦略を実現しているかを学びたいと思いました。
高等経営学講座で得たもの、学んだもの長年従事してきたB to Cビジネスとは異なる様々な分野のビジネスに関してのケースを通して経営戦略の要諦に触れることができました。グループ討議、クラス討議ともに限られた時間のなか、限られた情報で自分の分野外の案件を討議するため、前日の予習は非常に大変でした。分野外のテーマを自ら考え抜くこと、その考えを様々な企業の第一線で活躍している方々と論議することで深め、また逐次修正して自分としてのベストの結論を導くというプロセスを12ケース体験できたことは大変有意義でした。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていくか最適な経営判断によりビジネスを拡大することができたというサクセスケースのみならず、結論を先延ばしにすることでさらに傷が深まるケースも学びました。直接競合との関係だけにとらわれていると市場で起きている変化を見落とすことになる、マクロ視点での分析・判断が重要であることもケーススタディを通して体得しました。経済のグローバル化進行とともに市場環境変化が加速する中、素早い認知と分析、素早い判断、そして素早い実行が行える体制を社内で構築していきたいと思います。

第61回高等経営学講座
第61回高等経営学講座に参加して
泉 豊禄 氏(第61回高等経営学講座受講)
ハクスイテック株式会社 代表取締役社長
井の中の蛙にならないように
同じ場所で同じように仕事をしていると、日々の変化や問題に対応しているつもりであってもいつの間にか視野が狭くなってくるものだと思います。高等経営学講座の受講を思い立ったのは、まったく違う業種の方と議論を交わすことができたり、ケースを使ったインターアクティブな授業で新しいことを学ぶことができたりと、知識だけではなく考え方や視野を大きく広げてもらえるのではないかという期待からでした。
なるほど、そういう考え方もあるのか、という気づき
ケースを自分で読み込み、小人数のグループで議論し、そして先生を前に多めの人数で意見交換していく。この過程が重要でした。自分一人では気づかなかったことが小グループの議論で気づきとなり、そこで納得できたことがクラスの中で覆される、あるいはまったく気づかないことに気づかされる、といったことが繰り返されました。もちろん知識として新たに得るものも多いのですが、それ以上に「そうか、世の中は今こう動いているんだ。こんな考え方でこの会社は成功しているんだ。それにはこんな理由があるんだ。」といったことが、自分でやっていることの追認であったり否定であったり、そこに面白さを感じました。そして小グループでの連帯感がさらに楽しさを倍増してくれました。
まずはやってみよう、そして伝えよう
講座で学んだことは数多くあります。すべてが必ずしもすぐ実際の仕事に当てはまるわけではありませんが、まずは自社にしっくりくることからやってみようと思います。現場での実践、そして広く考え方の応用が可能であると思います。また、学んだことを社内で議論の土台として活用し、新たな環境変化への対応に生かしていきたいですね。私は特にハーバード大学のアナンド教授のクラスが深く心に刺さりましたので、まずはここから社内で共有していきたいと考えています。

第60回高等経営学講座
第60回高等経営学講座に参加して
野田 義夫氏(第60回高等経営学講座受講)
株式会社クレハ 企画本部本部長
日系の素材産業にとっても、今後、市場の需要拡大が期待出来る新興国をはじめとするグローバル市場に、競争熾烈な事業環境の下、変化のスピードに対し如何に革新的な事業戦略を展開していくかが重要課題となっている。当社も同様の状況に直面しており、素材メーカーとして技術差別化を図りながら、頑強な参入障壁を創設すべく、変化に対して常に挑戦する経営姿勢が求められている。このような会社を取り巻く環境の下、意思決定のためのプロセス形成をどのように図っていくか、既述課題の解決のヒントを得ること等が、KBS講座の受講目的であった。
KBS講座の中では、限られた時間と情報を与えられ、自分達がケースメソッドの企業の経営トップであったらどのように意思決定するかを、臨場感あふれる状態で集中的に考えることが出来たことは、実際の経営において修羅場を経験出来たのと同様の価値があるものと感じた。更に、自分では考え及ばなかった発想がグループとクラスの討議を通じて提起されたこと及び実践的なビジネス手法を学べたことが、大いに刺激になり有意義であった。
本講座で得たこととしては、「成功している企業は業績が良い時でも将来に備え常に変革に挑んでいること」、「人財育成にあたっては任せないと育成しないという最大のリスクをとることになること」等が挙げられるが、自社の経営にあたっても、これらを教訓として位置付け、積極的に推進すべく展開を図っていきたいと考えている。

第59回高等経営学講座
第59回高等経営学講座に参加して
姫野 昌治氏(第59回高等経営学講座受講)
株式会社大分銀行 取締役頭取(代表取締役)
少子化や若者の都市への移住等による生産年齢人口の減少は、高齢化問題とともに、これからの地域経済に様々な課題を提起していくことになるが、現状においても、後継者不足等で事業継続を断念する地域中小企業は後を絶たない。また、われわれ地域金融機関を巡る経営環境も、長期に及ぶ低金利政策に伴う収益低下傾向から脱却できず、日増しに厳しくなっている。
グローバル化やICTの急速な進歩と普及、広がる規制緩和、そして人口減少等、かつて経験しなかった幾つもの環境変化や構造変化に適応していくには、これまでの知識や経験だけでは解決が難しくなっている。しかし、抱えている課題は多い一方、職務がら休日の付き合いも外せないことから、じっくりと勉強する時聞が取れない。そのような中、KBSの本講座を知り、かかるジレンマを吹き飛ばすために思い切って参加した。
ポーターの「競争戦略論」等の経営書はこれまで読んではきたものの、本講座のようなケースメソッドによる企業分析、戦略立案など、より実践的な活用や応用について学べたことは有意義であった。また、ケースを材料にグループ議論を重ねたり、他グループや講師の意見を拝聴する中で、自分では発想できなかった様々なアイデアは大いに参考になった。
今、日本の多くの企業は変革を求められている。経営を変えるにはリスクが高まる。しかし、変えなければさらにリスクは高まる。本講座で得た経験を自社の経営に生かすべく、積極的に行動していきたい。

第58回高等経営学講座
知的な議論の体験的学習を初体験
塩野 秀作氏(第58回高等経営学講座受講)
塩野香料株式会社 代表取締役社長
2013年7月26日から9日間、帝国ホテル大阪で開催の第58回高等経営学講座に参加しました。
2つの会社の社長を兼務していた私は、日々、業務に追われ、経営の勉強はせず仕舞でした。そのような中、6年前に大病で長期入院、その際人生を振り返って、経営の勉強の必要性を強く感じ、各種セミナーに積極的に参加してきました。2013年になって第58回高等経営学講座の案内が届き、繁忙期ではない時期に開催だったので、受講を決めました。
受講者は80名で10グループに分かれ、前日に翌日授業の教材を読み込みます。グループ・ディスカッションでは自分が気づかなかったことに気づかされました。そして、授業は、講師による数々の質問に受講者が答えていく形で進行し、さらに議論を深めていくという知的な議論の場でした。こういう体験をもっと早くしたかった。頭は疲れるが知的な興奮状態が続いた9日間でした。
授業日の午後3時前後に、頭と身体の疲れをほぐしてくれる20分間の体操が組まれ大好評でした。同じグループになった皆さんは、業種も異なるし、年齢・役職も様々でしたが、何か戦友のような仲間意識が生まれ、年内には同窓会をする予定です。数々の経営事例を具体的に学習できたことや、友人ができたことは、得難い体験でした。必ずこれからの経営に役立つと確信しています。講師の先生方、事務局スタッフの皆さん、そしてホテルスタッフの皆さんに感謝しております。

第57回高等経営学講座
自分では考え付かないような発想や物事の見方がある
山岸 匠氏(第57回高等経営学講座受講)
クオール株式会社
コーポレートコミュニケーション部 執行役員 部長
私は2012年7月26日から8月3日にかけて帝国ホテル大阪で開催された、高等経営学講座に参加しました。
89名の参加者が10グループに分かれており、私のグループは8名だったのですが、様々な業種から来られた方々でしたので、非常に刺激をうけました。
セミナーの期間については、「もっと新しいことを学びたい」という思いが強くあり、それほど長いとは思いませんでした。中村教授担当のエーザイさんの中国に関するケースは非常に身近に感じましたし、様々な業種に関わるケースを使いグループディスカッションが盛り上がる中で、「自分では考え付かないような発想や物事の見方がある」という気づきがありました。
毎日午後5時20分にクラスが終わり、夕食後から午前1時、2時くらいまでグループで、或いは自分の部屋で翌日のケースを読む、というサイクルでした。たまたまロンドンオリンピックが開催されていましたが、勉強のかたわらオリンピックも気になり、本当に寝不足になりました。
同じグループの方々とは、セミナーが終わった後もみんなで集まっています。9日間という長い期間を共に過ごすことで、非常に深いつき合いになれます。

第114回経営幹部セミナー
第114回経営幹部セミナーに参加して
古川 慶子 氏(第114回経営幹部セミナー受講)
NRI社会情報システム株式会社 開発部 上級システムエンジニア
経営幹部セミナーを受講した目的
マネージメント、リーダーシップや幅広い発想力を他業種の方と交流しながら学習し、日々の課題への対応や知見を深めることを期待して参加しました。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだもの
10泊11日の長期にわたって職場から離れ、缶詰状態の環境の中で、経営、財務管理、生産管理、マーケティングなど幅広いケースについて、個人研究、グループディスカッション、クラスディスカッションと講師の方からのレビューを行うことで、独習で気付かなかった視点や知見を広めることができよかったです。
今後学んだものを職務でどのように活かしていくか
今回学んだことをお客様への提案や日々の課題に対応する際に振りかえり実践していきたいと思います。

第113回経営幹部セミナー
「幅広い視野で考えるきっかけと知識を得た11日間」
橘 典子氏(第113回経営幹部セミナー受講)
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
受講のきっかけは、勤務先の上司からの勧めで自主的ではありませんでしたが、提案を受け、セミナーについて調べたところ、「経営の基礎知識を体得」「横断的に自社の問題を解決に導く」 という言葉にひかれ、受講を決めました。
私は長くマーケティングの部署で仕事をしており、基礎知識のうち、財務、会計、組織マネジメントの知識が欠けていると常々思っていたことと、また仕事の幅を広げていきたいと考え始めていたことでタイミングも一致しました。
グループディスカッションでは、自分一人では考え及ばないことに気づかされたり、知識の豊富なメンバーから教えてもらうことも多く、貴重な時間でした。クラスディスカッションでは、さらにさまざまな考え方に出会い、多様な人間性を改めて認識しました。
日常の仕事からまったく離れて、ずっと考え続けたり、集中して物を読み続けるという経験は、本当に久しぶりでしたが、幅広い視野で考えるきっかけと基礎知識を習得することができたと思っています。
この経験を実際のビジネスで生かして行きたいと考えています。

第112回経営幹部セミナー
他業種の参加者とディスカッションできる方法が素晴らしい
立山 洋氏(第112回経営幹部セミナー受講)
ベルジュラックジャポン株式会社 代表取締役社長
経営幹部セミナーを受講した目的を教えてください?
会社の経営やビジネスの場で、それまでの多くの経験が判断を正確にし、それに伴う行動を的確にしていきます。しかしながら、同じような重要な経験をする機会は多くありません。
経営幹部セミナーで得たもの、学んだものは何ですか?
16の様々な実例を紐解き、自習・グループディスカッション・クラスディスカッションと言う順番で理解を深め、幅広い見方(分析の方法)・聞き方・話し方を学びました。自習時の自分の考え・分析を、他の業種の参加者とディスカッションすることで確認できる方法は素晴らしかったです。
今後、学んだものを職務でどのように活かしていきますか?
ケースメソッドで多くの実例を学んだ経験やグループメンバーとの意見交換・交流を含めて、今後のビジネスの場でスピーディーに的確に生かしていけます。

第110回経営幹部セミナー
超濃密な11日間
~ケースメソッドの想像以上の効果と受講生との出会い~
福薗 健司氏(第110回経営幹部セミナー受講)
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社
様々な視点から物事を俯瞰する能力を身につけたいと考え、私はこの研修に参加した。10泊11日という期間、職場を離れることの不安もあったが、それ以上に得られる効果に期待し、研修初日を迎えたことを昨日のことのように思い出す。
「その企業の成功要因は?」、「将来取るべき戦略は?」、「財務諸表の特徴は?」・・・
実在する企業の具体的な行動について自分自身の考えを前日まとめる。翌日、様々な業種の受講生と行うグループ・ディスカッションでは、業種を超えた部門横断的な視点で戦略を考えることができる。その後の講師による授業は、講師・受講生双方での対話による協働作業により展開され、経営戦略のフレームワークなどをより実践的に学ぶことができる。これこそがケースメソッドの効果と言える。
上記体験を通して、より多角的な視点で企業行動を考えられるようになっている自分自身の変化を日々実感する。グループ・ディスカッションの内容も日々高度化していく。その結果、講師による授業も自然と内容の濃いものとなっていき、好循環が生まれてくる。
10泊11日という長い期間、そういった環境に身を置けたことで、当初設定した研修の参加目的以上のことを身につけることができたと実感している。そして、研修後も交流を持てる数多くの仲間を得ることもできた。そのような意味も含め、この研修に参加できて本当に良かった。

第110回経営幹部セミナー
斬新な授業と想像を超えた発想との出合い
平田 喜裕氏(第108回経営幹部セミナー受講)
株式会社日本経済新聞社
「これが最先端のビジネススクール教育か!」――。企業活動の実際の「ケース」を教材に、講師と受講生が経営判断を議論する授業方法(ケースメソッド)がとても斬新でした。授業に先立ち、個人予習とグループ討議を行う点も合理的といたく感心しました。
私は日本経済新聞社で30年にわたり国内外で記者あるいは編集者として仕事をしています。KBSの研修に参加することになったのは、外から経営を取材するだけではなく、内側から経営を経験するためです。これまでとは異なる頭の使い方、物事の見方を身に付けようというわけです。
目的は達成できたと考えています。授業はもちろん参加者どうしの合宿生活を通じ、新しい視点や想像もつかなかったような考え方に出合うことができました。どのような業種から、どのような階層の方が参加しても刺激になるだろうと思います。
今回の研修では、ケースの作成にわたしどもの報道が参考になっていることも知りました。こんな使われ方もあるんだ、と。正確かつ公正な報道を心がけるべく改めて気が引き締まったのも予期せぬ成果でした。

2015年度週末集中セミナー
物事を違う視点から見る面白さ
山田 昌代氏
(2015年度週末集中セミナー ヘルスケアポリシー&マネジメント集中コース受講)
横浜栄共済病院
代謝内分泌内科部長
医者として仕事を続けるうちに、気が付いたら診療だけでなく病院内の栄養部門などでの管理的な仕事が増え、戸惑うことが多くなりました。そんな中、KBSの卒業生の方と接する機会があり、物事を違う視点から見る面白さを教えていただきました。何とかそれを学ぶ機会はないかと探しているうちにこのセミナーを発見しました。実際に参加させていただいて、全く違う業種の方との交流が非常に新鮮で刺激的であっただけでなく、ケースを通して学んだ"small start with big picture"ということが、自分が抱える案件についても応用して早速使うことができることに感動いたしました。週末開催ということも私にとって大変魅力でしたが、今回は小学生の息子の学芸会よりこちらを優先し、恨めしい顔をされながらも(笑)、受講して本当によかったと思っています。3回で1つの分野というボリュームも程よく、現在別のコースの受講を計画中です。

2015年度週末集中セミナー
経営理論で介護サービスの先駆者に
神山 重子氏
(2015年度週末集中セミナー ヘルスケアポリシー&マネジメント集中コース受講)
医療法人啓和会 常務理事
今回セミナーに参加したきっかけ
かねてより田中滋先生の講演会等に参加したり、私どもの啓和会グループを見学にいらして頂いたりとヘルスケアマネージメントの第一人者でおられる先生のお話を伺う機会がありました。 田中先生の今後の講演予定を調べていたところKBSの存在を知り、参加させていただく運びとなりました。
参加させて頂いた感想
医療法人と言えども企業経営に相違はなく、いかに情報を入手し、それを効率よく運営していくかで将来像も変化してくる時代です。直感的に経営していたものを大企業や外資系企業の合理性を取り入れ、理論に基づきシステム化できれば人材も更に輝き、地域や社会に奉仕できるとの希望を持ちました。学ぶ機会は将来にわたり、重要なチャンスであり、未来が開ける第1歩だと思います。この研修を契機に21世紀のアジアにおける介護の先駆者としての日本企業の1つとなりたく邁進してまいります。
ナビゲーションの始まり
