2025年11月20日
【EMBA】スター・マイカ・ホールディングス 水永政志社長に学ぶ
― 「再現性」と「非模倣性」を備えた経営モデルの真髄
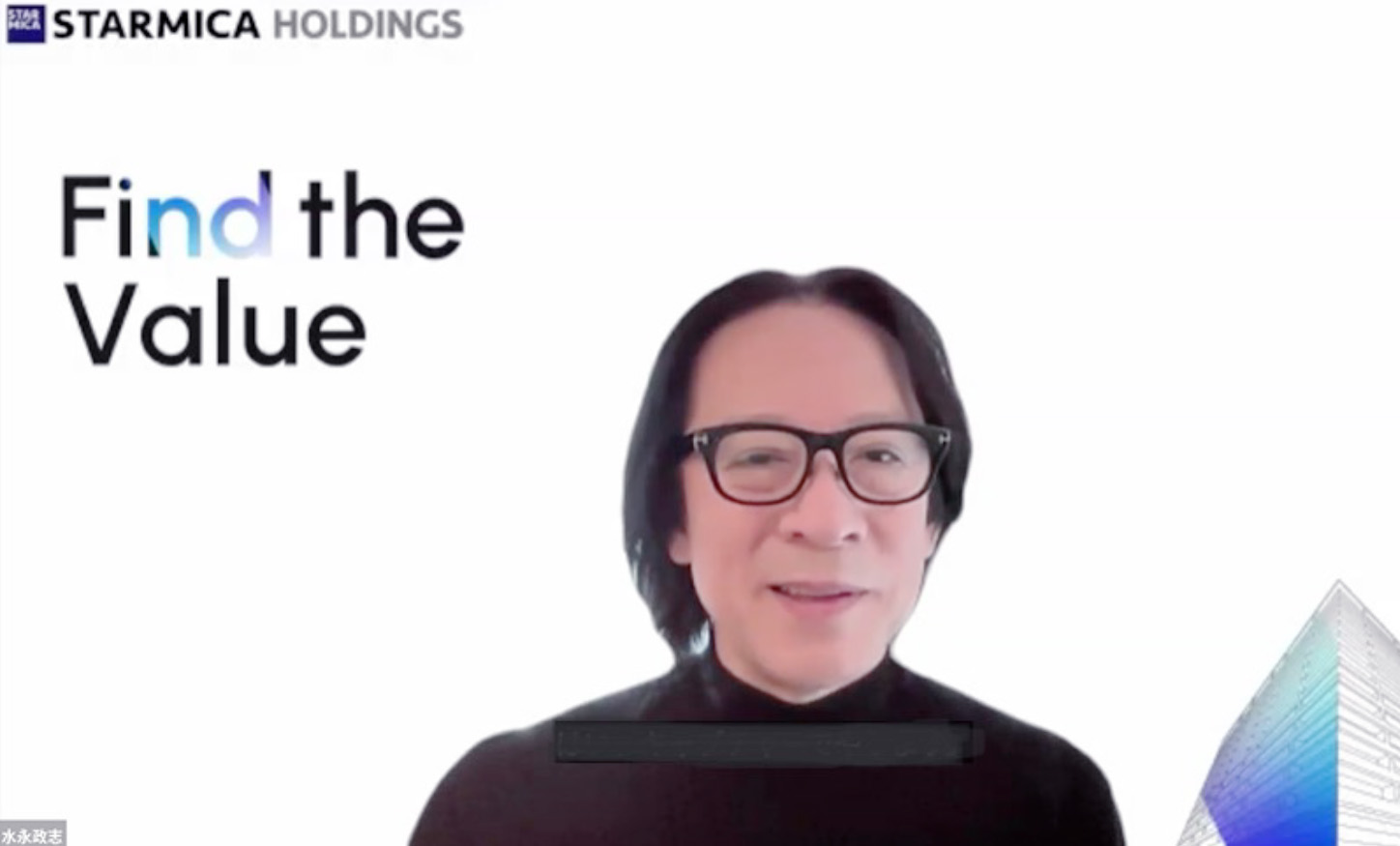
2025年10月17日、「経営者討論A」(第5回)が開催され、スター・マイカ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長の水永政志様をお迎えし、ご講演いただきました。
講義では、東京大学在学中の起業から三井物産、BCG、ゴールドマン・サックスを経て、三度の起業で上場企業を創出された水永社長が、「キャリア」「ベンチャー」「再現可能なビジネスモデル」について、理論と実体験の両面から熱く語られました。
後半では、2014年に中村教授らが作成したKBSケース「スター・マイカ株式会社」を題材に、直近の決算資料にも触れながら、「スター・マイカのビジネスモデルはなぜ他社に模倣されなかったのか」「2014年当時の経営課題は解決されたのか」というテーマについて、水永社長ご自身が解説。過去と現在をつなぐ貴重な学びの機会となりました。
当日は、欧州ご出張の合間を縫ってリモートでご登壇いただきましたが、学生からの質問が相次ぎ、画面越しでも熱気あふれる場となりました。
ベンチャーの本質 ― 挑戦の裏にある「痛み(ペイン)」と「学び」
講演は、「なぜベンチャー企業が成長するのか?」という問いから始まりました。水永社長は、社会のアンメットニーズを見つけ、それを解決するソリューションを構築することこそがベンチャーの使命であると語られました。また、「思いついても『自分には無理だ』と思い込む人が多い。殻を破る勇気こそが起業の第一歩」との言葉は、起業や新規事業立ち上げを志す学生の心に響きました。
さらに、「成功には理由がないが、失敗には理由がある。先輩から学ぶべきは『失敗』である」との指摘も印象的でした。ご自身の経験を踏まえ、起業や経営における「理屈」と「行動」の重要性を強調し、経営学は単なる理論ではなく「行動の哲学」であると説かれました。
三度の起業が教える経営のリアル
学生時代の創業から、外資系投資銀行での華やかなキャリアの裏には、「死にそうになった」と語るほどの資金難や経営危機があったと、水永社長は振り返ります。
特に印象的だったのは、「勉強していなかったことで会社の"時価"を理解できず、簿価で売却してしまった」という初期の失敗談です。そこから得た教訓は、「知らないことは損すること。勉強が一番儲かる」という極めて実践的な言葉でまとめられました。
続くスター・マイカ創業では、前例のなかった「賃貸中の分譲マンションを購入・再販する」ビジネスモデルを確立。法律上退去を強制できないという不動産業界の"常識"を逆手に取り、賃貸中の資産価値と流動性をデータ分析によってモデル化。結果として、業界内で唯一無二のポジションを確立し、上場を果たし、2011年にはポーター賞を受賞しました。
再現性のあるビジネスモデルとは何か
講演後半では、スター・マイカ社の事業構造を題材にケース討議を実施。
水永社長は、同社の成功要因を「偶然の発見ではなく、問題を解くプロセスの積み重ね」と説明し、参入障壁の本質を「努力と検証の積層による"非模倣性"」にあると解説されました。
また、同社が構築したポートフォリオモデルや金融機関との協働スキームを例に、「ファイナンスの理解こそが成長を支える基盤である」と強調。データドリブン経営とリスク管理の両立という視点からも、多くの示唆を得る講義となりました。
学生へのメッセージ ― 「後悔しない自分の人生を生きよう」
質疑応答では、「なぜゴールドマン・サックスでの成功を手放し、再び起業を選んだのか」という質問が投げかけられました。
水永社長は、「当時は非常に悩んだが」と本音を語りながらも、「Live Your Own Life ─ 自分の人生を生きたいと思った。やらなければ一生後悔すると思った」と当時の決意を語られました。
また、「成功は運によるが、運を高めるのは勉強。失敗の確率を下げることが経営者の努力である」と述べ、再現性ある成功には"理論"と"修練"の両輪が不可欠であることを強調されました。
利己と利他の両立 ― CSV経営の実践
別の質問に対して、水永社長は、「利他と利己は対立しない。社会のためになる事業ほど収益性が高い」と語り、マイケル・ポーター教授のCSV(Creating Shared Value)理論にも言及。自分がやりたいことと、社会に貢献し社会的な価値がある事業の接点を探し出すのが経営者の役割であると伝えました。スター・マイカ社では、アービトラージ投資モデルの実践に関心がありましたが、中古住宅の再流通を通じたCO₂削減やサステナビリティへの貢献は、結果として企業価値を高めることにもつながったとご自身の事例を述べられました。
まとめの言葉
講義の締めくくりとして、水永社長は「派手な事業は廃れる。再現できる成功こそが本物のビジネスモデルである」と語り、「勉強を続ける癖をつけることが大事だ」と繰り返されました。経営者としての本音に触れ、理論と実践の融合を体現する数々の言葉は、私たち学生にとって大きな励みとなりました。長期的に持続する経営のあり方を学ぶ、極めて密度の高い講義となりました。
E11 久世 浩司

